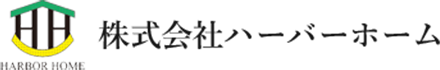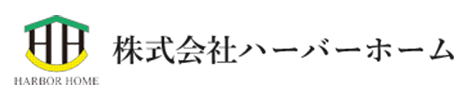疑問や質問に丁寧な回答で不安を減らす
FAQ
生前対策に関する問題から認知症対策や空き家相談、相続手続きや不動産売却など、様々な相続や不動産の問題や売買などに関する疑問など、多くお寄せいただいたご質問に回答しています。また、回答項目になかったご質問や疑問などがございましたら、LINEから疑問や質問などお気軽にお問い合わせください。
生前対策
- 【生前贈与】毎年贈与をするときに贈与契約書を作っているので、後から税務調査などで指摘されることはありませんよね?
- 贈与契約書は、お互いの合意があったのを確認する書面として有効ですが、後から作ろうと思えば作ることは出来ますので、税務署も絶対的な証拠だとは考えていません。
贈与契約書の証拠能力を高めるやり方は、公証役場で確定日付をもらっておくと、その日付にしかもらう事が出来ないので証拠能力が上がります。
ちなみに、1通700円で出来ます。
- (公正証書遺言の検索)父から公正証書遺言を作成していると聞いていたのですが、兄が教えてくれません。公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることはできますか?
- 平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報が管理されており、全国の公証役場で、遺言公正証書の有無及び保管公証役場を無料で検索することができます。
遺言検索の申出は、相続人等の利害関係人のみが公証役場に対してすることができ、必要書類は、遺言者が死亡した事実を証明する書類、遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、申出人の本人確認が必要になります。
- 【生前贈与】子どもが生まれて、新築住宅を購入予定です。 妻の両親からの援助に住宅取得等資金の贈与の非課税制度は使えますか?
- 自分の父母や祖父母から援助を受けた場合には、「住宅取得等資金の贈与の非課税」の特例で一定額が非課税となりますが、配偶者の父母や祖父母からの援助は、この非課税特例の対象外です。
- 【生前贈与】孫の教育資金として孫名義の口座に毎月振り込みをしていますが、問題ないでしょうか?
- 孫名義の口座に振り込みをしていても、通帳や印鑑は祖父母が管理しているという場合、『名義預金』と判断され、孫への贈与にならず祖父母の財産とみなされます。
- 【遺言】遺言書を作るときは、家族全員で相談するべきでしょうか?
- 相談するのは「法定相続人全員」であって「家族全員」ではないことに注意し、長男の嫁や長女の婿、孫など、家族であっても、法定相続人でない人を呼ぶべきではありません。
相続とは関係のないことまで話し合いが及び、もめやすくなる恐れがありますので、同席すべきはあくまでも父、母、子供たちだけにしておきましょう。
- 【遺言】父の遺言書を作るときに、後で兄に父は認知症だったので遺言書は無効だと言われないようにしておきたいのですが・・・
- 遺言の方式としては、公証人が証人2名の立会いのもと、遺言者の口述を公正証書にする公正証書遺言が最も望ましいといえます。
さらに、遺言作成前後に長谷川式認知スケールで認知能力を測定しておき、主治医に診断書を作成してもらうことや介護記録を保管することで、遺言作成時に遺言能力があったことを証拠化することも有効です。
- 【生前贈与】夫の実家に帰省中、義父が孫に使ってと300万円を渡してくれたのですが、非課税で受け取る方法はありますか?
- 祖父母など直系尊属から子や孫への「教育資金の一括贈与」は、一定の要件を満たすことができれば、最大1,500万円まで非課税扱いになります。
教育資金の特例を使わない、あるいは手続きが未了の場合は暦年課税が適用され、1年間に受けた贈与の合計から基礎控除110万円を差し引いた額が課税対象となります。
教育資金の非課税制度の利用を選択するのであれば、金融機関で「教育資金管理契約」を締結後、専用口座を開設し、申告書を提出する必要があります。
- 【生前贈与】祖父から贈与を受けた金銭で土地を購入し私名義に、建物は夫が銀行からの借入金により取得し夫名義にした場合、。住宅取得資金の贈与の特例を受けることはできますか?
- 住宅取得資金の贈与は、贈与を受けたお金で新築等をする建物の土地の取得に充てる場合も対象になります。
ただし、その取得した土地の上の建物の所有権も取得しないと、住宅取得資金の贈与の適用を受けることはできません。
- 【生前贈与】贈与をする際には、毎年違う日付にすれば、定期贈与にならないんですよね?
- 毎年同じ日付に生前贈与をしても、定期贈与にはならないので問題ありません。
定期贈与というのは、例えば1,000万円を贈与する為に、100万円を10年かけて贈与するというもので、贈与契約書の中に1,000万円を贈与するために、毎年100万円ずつ贈与するような内容が入ってる場合に適用されますが、100万円を贈与するという内容の贈与契約書を10年間作れば、問題はありません。
- 【生前贈与】生前贈与をする場合、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択すべきですか?
- 相続開始時の遺産総額やタイミングで変わってきますが、自分がいつ亡くなるかなどは誰にもわかりません。
平均寿命が想定になり、平均寿命の7年を切るまでは暦年贈与を最大限利用することが有利であり、そして、平均寿命の7年を切るタイミングで相続時精算課税に切り替え、以後、毎年 110 万円の相続時精算課税の基礎控除の贈与を継続するのがベストと考えられています。
- 【生命保険】父の生命保険料を、息子が払っています。生命保険の非課税枠を使えますか?
- 保険契約者が保険料を支払うのではなく、第三者が支払ってる場合は『名義保険』になり、非課税枠としては認められません。
相続税の税務調査では、名義預金も問題になる事が多いですが、名義保険も問題になる事が多いので注意が必要です。
- 【生命保険】生命保険に加入していれば、すべて非課税枠が使えるということですか?
- 生命保険に加入していれば、どんな場合でも非課税枠が使えると思っている人もいますが、そうではなく契約者と被保険者が同じ場合に、使う事が出来ます。
契約者と受取人が同じ場合、契約者と被保険者と受取人が全て違う場合には、非課税枠は使う事は出来ません。
生命保険を取り扱う人の全てが知っているはずですが、わかっていない保険外交員もいるようですので、注意が必要です。
- 【生命保険】生命保険の受取人を孫にしておくのは、良くないと聞きましたが・・・
- お薦めできない理由は、3つあります。
1つ目は、非課税枠は法定相続人限定なので法定相続人ではない孫は、生命保険の非課税枠が使えません。
2つ目は、被相続人の一親等の血族および配偶者ではない孫は、相続税が2割加算されます。
3つ目は、孫は暦年贈与の持ち戻しの対象外ですが、みなし相続財産の生命保険を受け取る事で、持ち戻しの対象になります。
生命保険の受取人は、子供にしておくのがお薦めです。
- 【生命保険】生命保険の受取人を妻にしているのですが、あまり良くないと聞きましたが・・・
- 相続税の節税対策で、配偶者は生命保険の受取人に向かない理由は、生命保険の非課税枠を使わなくても配偶者の税額軽減(配偶者は1億6000万円まで相続税がかからない)が使える事です。
しかし、万が一の事が起こった時に、持っている現預金などでは足りず、配偶者が生活を出来なくなってしまう場合、その足りない分を保障として用意するなら、受取人を配偶者にすることもあります。
- 【遺言】私達には子供がいなくて、両親は亡くなっていますが、私には兄弟がいます。妻に苦労をさせてきたので、全財産を妻に相続させたいのですが・・
- この場合遺言を作っていなければ、配偶者と兄弟が相続人になります。
兄弟も突然財産が貰える事になって、頂けるものは頂きたいという気持ちになり、意見がまとまらず争いになることはよくあります。
遺言を作っておけば、兄弟は別生計であることが一般的であり、遺産を相続できなくても生活に困ることはないと考えられているため、遺留分はありませんので全財産を配偶者に相続させることができます。
子供のいない夫婦で配偶者を守りたいと思ったら、必ず遺言を作っておきましょう。
- 【遺言】我が家は妻と子供が1人の3人暮らしですが、その場合でも遺言は必要でしょうか?
- 相続税がかかる人で、子供に法定相続分以上に残したい場合は、遺言を作っておいた方が賢明です。
理由は、配偶者が認知症になったら、後見人を立てることになり、子供は法定相続分でしか相続出来なくなるからです。
二次相続に備え、子供に法定相続分以上残したいときは、子供が1人の場合でも遺言は必要です。
- 【生前贈与】高収益の賃貸不動産を贈与すると節税率が上がると聞きましたが・・
- 高収益の不動産を相続人に贈与すると、賃料を相続人に移すことで、所得の分散効果も期待でき所得税の節税にもなり、賃料が納税資金にもなることで節税率が上がるということです。
- 【生前贈与】確実に将来値上がりする不動産を、事前に贈与すれば有利と聞きましたが・・・
- 相続時精算課税贈与では、贈与した時期の時価で計算されるので、評価額の低いうちに贈与することや将来の高収益が確実に見込まれる財産を贈与することが有利とされます。
(一例)
① 市街化区域の土地で、現在は倍率方式であるが、将来路線価方式になる可能性がある土地。
② 現在は市街化調整区域であるが、近い将来、 市街化区域へ変更される可能性がある土地。
③ 新駅設置予定や都市開発計画があり、便利になるため地価が上がると思われる土地。
認知症対策
- 【後見人制度】任意後見人制度と法定後見人制度の違いは何ですか
- 『任意後見人制度』は本人にまだ判断能力があるうちから、契約により信頼のおける第三者に財産管理を任せることができる制度です。
『法定後見人制度』とは、判断能力が不充分になると家庭裁判所から法定後見人が選任され、本人の財産を管理することになる制度です。
法定後見人には家族が選任される可能性は低く、ほぼ弁護士・司法書士が選任されますが、士業であるため安心感はありますが、絶対的とはいえません。
- 【後見人制度】認知症対策として『任意後見契約』をしていれば安心して良いですか
- 認知症対策には、「身上監護」ご本人の生活を維持することや療養看護に関することと「財産管理」が基本になっています。
「任意後見制度」を利用した場合、後見人はご本人の身上を保護する職務はありますが、 財産管理の面ではご自分で信頼して選んだ後見人にも関わらず、不動産の売却、アパートの建て替え、大規模修繕、銀行借入れなどの相続税対策は、家庭裁判所の許可が下りないことが通常です。
また「家族信託」は、財産管理が目的であるため、任意後見制度と違い家庭裁判所の許可は必要ありませんが、身上保護の権限がないため対応できません。
そのため、「任意後見制度」と「家族信託」の併用が必要になってきています。
- 【後見人制度】現在、介護施設に入所しています。
いつもお世話になっているケアマネジャーに後見人になって欲しいと思っているのですが、後見人になってもらえるでしょうか - 利用している施設のケアマネジャーは、本人が利用するサービスを提供する会社や団体に所属しているので、その会社や団体に所属する人のミスで本人が怪我をしてしまうような事があれば、会社や団体と本人は利益相反関係になります。
ケアマネジャーは、給料を貰っている立場上、会社や団体側につかなければいけない事もあるので、本人を支援している関係者などは、後見人には選ばれません。
- 【後見人制度】 親の認知症が進んだので成年後見制度を利用し、後見人に司法書士の人になってもらったのですが、 心配になり後見人に通帳を見せて下さいと言いましたが、見せられないと言われました。使い込みでもしてるのかなと心配になりますが・・・
- 子供であっても、通帳の中身を公開する義務はありません。
例えば、銀行に行って、親の通帳の中身を教えてくださいって言っても教えてもらえないのと同じです。
ただ、後見人が子供に通帳の中身を共有した方が良いと思えば共有してもらう事も出来ます。
- 【後見人制度】任意後見契約を結んだのですが、その方で良かったのか後から心配になっています。
誰を後見人にするか考え直したい場合、契約の解除は出来ますでしょうか? - 任意後見監督人の選任前なら合意が無くても解除出来ますが、任意後見監督人が選任されると解除は出来なくなります。
後見監督人が選任されているという事は、判断能力が不十分な状態だからです。
- 【生命保険信託】私はシングルマザーで子供が1人いるのですが、子供は障害を抱えています。
私が認知症になったときに家族信託が使えないと聞きましたが、何か良い方法はありませんか? - 信じて託す受託者がいない場合、家族信託は使えません。
そんな時に選択肢になるのが、生命保険信託です。
生命保険信託の信託会社が受託者となり、信託契約の内容を確実に遂行してくれますので、信じて託す家族がいなくても安心です。
- (死後事務委任契約)70代独身、弟がいますが絶縁状態で自分の死後が不安です。私の葬儀や納骨、遺品整理などは、弟に頼むしかないのでしょうか?
- 葬儀や納骨、遺品整理だけでなく、行政手続きや各種契約の解除手続きや各種費用の清算などさまざまな手続きをしなければなりませんが、これらの事務を、司法書士、弁護士などに死後事務委任契約で任せる方法があります。
委託の内容を明確にして公正証書で契約を結びますので、費用は発生しますが、死後の事務手続きに関する心配はなくなります。
- (予約型代理人サービス) 私の財産に不動産は無く、銀行の預貯金だけです。成年後見は負担が重く、家族信託は専門的でハードルが高いので、何か良い方法はありませんか
- 金融機関の予約型代理人サービスという制度があり、本人が認知症になったあとでも、家族が銀行窓口で預金を管理できる仕組みです。
本人の判断能力があるうちに代理人 (原則として2親等以内の親族)を銀行に届け出て、認知症になったら代理人が医師の診断書を提出し、診断書が受理されると、代理人はATMでの入出金、窓口での預金払い出し、定期預金の解約、投資信託の売却、住所・連絡先の変更などの諸手続き取引が可能になります。
費用や裁判所の手続きが不要で、専門家に依頼する必要がないのですが、すべての金融機関が導入しているわけではないので、利用を検討する際には、本人のメインバンクが対応しているか確認することが重要です。
- 【見守りサービス】親が遠隔地に住んでおり、ときどき電話をしているのですが、認知症の進行具合が心配です。何か良い対策はありますが?
- ときどき電話をする程度では進行具合はなかなか把握することはできませんので、見守りサービスなどのご利用をお勧めします。
『見守りサービス』とは、定期的に本人の自宅を訪問して面談することにより、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するためのサービスです。
お住いの自治体のほか、郵便局員や宅配の配達員による安否確認サービスやセキュリティ会社などの人感センサーを使った見守りサービスなどがあります。
- 【財産管理】認知症と判断されると、個人の財産管理はどうなりますか。
- 認知症と判断されると財産は凍結され、高齢者施設に入居するために預金を引き出すことも、自宅を売却することもできなくなり、たとえ家族であっても個人の財産は、解約することも処分することもできなくなります。
判断能力はあるが、身体能力が低下して財産管理ができないときには、自分が信頼できる人に財産を管理してもらう『財産管理委任』という制度があります。
判断能力があるうちに自分で後見人を選び、判断の能力が低下したときに後見人に財産を管理してもらう『任意後見制度』のご利用もご検討ください。
空き家相談
- 【特別控除】相続した空き家の売却を検討しているのですが、(相続空き家の3000万円特別控除)を簡単に教えてください
- 亡くなられた人が40年前に900万円で買った土地を4,000万円で売却した場合で、建物の取り壊し費用が100万円かかったとします。
その場合、売却益は4,000万円-(900万円+100万円)=3,000万円。
売却益3,000万円にかかる税金は、所得税が3,000万×15%=450万円、住民税が3,000万×5%=150万円
納める税金は合わせて600万円。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円の控除を使うと、売却益3,000万円を控除でき、支払う税金は0円になります。
大変優遇されたこの制度ですが、適用にはいくつかの要件をみたすことが必要です。
- 【特定空家】「空き家の固定資産税が6倍になる」は本当ですか?
- 行政の指導に応じず「特定空家」と認定され、問題があると見なされた空家には、所有者に対して不動産管理の指導・勧告・命令を実行できるようになりました。
指導に応じない場合は、固定資産税の特例が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍になったり、空家の所有者に対して50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
また、行政が所有者に代わり不動産の解体を行う場合は、当然かかった費用は所有者が全額負担しなければなくなり、数百万円の支払いが必要となるケースもあり、支払えない場合は土地や財産の差押えが行われる可能性もあります。
- 【維持管理】両親が亡くなり地方に相続した空き家がありますが、維持管理にかかる費用はどれくらいでしょうか?
- まず土地建物に対してかかる固定資産税、維持するには定期的な清掃や草刈り、修繕が必要です。
空き家の管理を業者に委託する場合、月数千~数万円がかかることもあります。
清掃等に水や電気を使うため、使わない月があっても、基本使用料は支払う必要もあり、火災保険や地震保険などの保険に加入する場合は、保険料の支払いも必要になります。
敷地が60坪で建物30坪位でも、少なくとも年間20万円はかかると見積もっておく必要があるでしょう。
- 【空き家のリスク】相続した実家を空き家にしたままなのですが、何をどうすればいいですか。
- 長い間空き家になっていると、不審者の侵入などの「防犯上のリスク」、ごみの不法投棄による「衛生上のリスク」、老朽化した場合の「倒壊のリスク」があります。
国にお金を出して引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度がありますが、いろいろな基準をクリアしなければいけないので使い勝手がよいと言えない状況です。
最近では空き家バンクの利用が積極的になってきており、民間と行政の支援も積極的になってきていますので、利用の選択にいれてもよいのかと思われます。
相続手続き
- 【債務調査】疎遠になっていた独身であった叔父が亡くなり、弁護士から『財産を相続されますか』と連絡があったのですが、叔父に借金がないか心配なのですが・・・
- まず、自宅の郵便物に債権者からの請求書や通帳引落をされていないか確認し、不動産があれば登記簿謄本を取得し、抵当権が設定されていないかを確認してください。
また、相続人であれば亡くなった方に負債があるかを、信用調査機関(JICC・CIC・KSC)に問い合わせる方法がありますが、個人への借入、保証人になっている場合は細心の注意が必要です。
- 【相続放棄】相続したくないので、そのままにしておいても大丈夫でしょうか?
- 相続することを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしないと、相続を承認したことになります。
また相続放棄をする前に、少しでも相続財産を受け取ってしまえば、相続放棄は出来なくなりますので注意してください。
また、遺産分割協議で財産放棄する方法もありますが、後で借金が見つかったときは、遺産分割協議で財産放棄したとしても債権者から借金を請求されます。。
- 【財産調査】先日母が亡くなりましたが、母の財産をどうやって調べればよいですか?
- 不動産をお持ちの場合は、固定資産税の納税通知書から所在地や地番、家屋番号を確認し、法務局で登記事項証明書を共同担保目録付きで取得します。
また、市区長村役場で「名寄帳」を取得し、持っている不動産の一覧を確認 します。(令和8年2月2日から「所有不動産記録証明書」が法務局で取得可能予定)
預貯金は、通帳やキャッシュカードから取引のある金融機関に問い合わせをし、金融機関がわからない場合は、生活圏内のすべての金融機関に照会します。
※マイナンバーを金融機関に登録しておくことで、相続開始後、一つの金融機関で全ての預貯金の調査が可能になる制度もあります。
- 【財産調査】不動産と銀行の預貯金は判明しましたが、株や生命保険はどうやって調べればいいですか?
- 株は証券会社からの報告書を元に、取引のある証券会社を調べます。
また、「証券保管振替機構」に登録済み加入者情報の開示請求を行い、証券会社や信託銀行の一覧を取得することもできます。
生命保険は、生命保険協会を通じて、生命保険契約照会制度を使い、亡くなった人に関する生命保険契約の有無を一括で照会できます。
- 【口座凍結】人が亡くなると、銀行口座はすぐに凍結されるのですか?
- 人が亡くなったという情報が役所と銀行で共有されている訳ではないので、自動的に凍結する訳ではなく、銀行が死亡の事実を把握した時に凍結されます。
取引銀行の職員が、外回りの際に葬儀を見かけたなどで把握されてしまうことはありますが、相続人側から伝える事で口座をを凍結させる事がほとんどです。
普通預金は暗証番号がわかれば、キャッキュカードで引き出しできますが、定期預金等の解約は本人の意思確認が必要になるところがありますので、注意が必要です。
- 【分割前の払戻し】どのタイミングで、銀行に届ければよいのでしょうか?
- 葬儀費用や医療費の支払いは、大きな金額が出ていく事もありますし、生活費の引き落とし口座になっている場合もありますので、事前に必要な手続きを終えてから、手続きを行うことが望ましいです。
また、口座が凍結された後でも、『遺産分割前の相続預金の払戻し制度』があり、1金融機関につき最大150万円までであれば、相続人1人だけで手続きができます。
- 【遺産分割】遺産分割協議の重要なポイントは・・・
- 相続税を多く払うか少なく済ませるかの最大のポイントは遺産の分け方なり、誰が何をいくら相続するかによって、何倍にも変わる税金です。
小規模宅地の特例や配偶者控除の税額軽減を考慮し、家族全体で最も相続税が少なくなる遺産の分け方を考えていきます。
不動産の分割では、相続評価額よりも時価がほとんどの場合高くなるので、必ず時価に換算して上で協議してください。
- 【相続税申告】相続税の申告を、毎年確定申告をお願いしている税理士に相談しようとおもっているのですが・・・
- 税理士にも得意分野があり、確定申告は所得税法ですので、相続には相続税法を専門とする先生にお願いしましょう。
昔からのお付き合いもあるという理由だけでは、お薦めできません。
電子申請を使わず、手書きで申告している税理士は特に注意が必要です。
- 【名義変更】夫が亡くなりました。不動産や銀行口座の名義変更、株と投資信託の口座は私の名義に変更すればよいですか?
- 不動産の所有者が亡くなった場合は、相続人への名義変更を行う相続登記の手続きを法務局に申請します。
銀行の預貯金は名義変更ではなく、解約払い戻しを受けることになります。
株や投資信託を保有していた人が亡くなった場合、そのまま引き継ぐことはできませんので、死亡届出書などを提出し、亡くなった人の口座から相続する人の口座に移管するか、相続する人が新たに口座を開設し移管するかのどちらかになります。
- 【税務調査】税務署はどうやって死亡情報を把握するのですか?
- 市区町村で死亡届が提出されると、その情報を翌月末までに所轄の税務署に通知するよう法律で定められています。
この情報は、国税総合管理システム(KSK)に集約され、相続税の時効を防ぐための重要なデータとなります。
不動産や収入情報も含め、税務署は相続税を適正に徴収するための調査を行い、必要に応じて銀行口座や現金の動きを徹底的に調査します。
残念ながら相続税申告をしなくても、逃げ切れるということはありません。
- 【税務調査】税務調査で「タンス預金」が見つかる理由とは?
- 国税総合管理システム(KSK)は、国民一人ひとりのおおよその財産状況を把握していて、申告した金額とシステム上の金額に差異がある場合、税務調査の対象となる可能性が高まります。
調査が始まると、税務署は金融機関に過去10年分の入出金内容を提出させることができ、多額の現金引き出しがあれば「タンス預金」として疑われ、必ずといっていいほど発見されます。
- 【家裁調停】相続人のあいだで遺産分割協議がまとまらない場合は、どうすればよいでしょうか?
- 遺産分割の協議に合意が得られないときは、家庭裁判所に調停および審判を申し立てて分割してもらうことができます。
裁判官1人と調停委員2人以上で構成される調停委員会が調停にあたり、調停で話し合いがまとまらない場合は、調停は不成立となり、裁判所の審判により遺産分割が決定されます。
審判は、法定相続分を基準としつつ、特別受益や寄与分および各相続人の職業、その他一切の事情を考慮して分割方法を決めます。
この審判に不服があれば、不服の申し立てをして高等裁判所で争うことになります。
- (未成年者相続)夫が亡くなり、私と未成年の子供2人が相続人です。遺産分割はどうすれば良いでしょうか?
- 相続人が未成年者である場合、親権者が法定代理人として遺産分割協議をすることになりますが、親権者(妻)と子供が共に相続人であったり、2人以上の兄弟姉妹が未成年で、同じ親の親権になっている場合、親権者(妻)と子供、または子供と子供の利益が相反する可能性があるので、親権者は代理人になれません。
その場合は、親権者は家庭裁判所にその子供の特別代理人選任の申し立てを行い、家庭裁判所の審判によって選任された特別代理人が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書への署名・押印などを代行することになります。
- (失踪宣告)相続人の一人が行方不明の場合、遺産分割協議はどうすれば良いでしょうか?
- 行方不明状態がいる場合、家庭裁判所に申し立てて失踪宣告の審判により、行方不明になってから7年経過したときに死亡したものとみなされます。
失踪宣告ができない場合は、家庭裁判所に申し立て、行方不明者の財産管理人を選任してもらい、その管理人が遺産分割協議に参加します。
ただし、管理人が遺産分割協議に同意するには家庭裁判所の許可が必要になります。
- (共有持ち分登記)親が所有していた不動産を相続登記するのですが、兄弟3人の共有名義でもよいでしょうか?
- 相続時は仲が良くても、時間の経過によって相続人の生活が変化したり、さらなる相続の発生によって事情が変わったりすることで意見が割れる可能性があります。
共有持ち分は単独で売却することができますので、知らない第三者が突然「共有者」として登場する可能性もあるので、できる限り早く共有物分割協議を行い、単独名義にすることをお勧めします。
不動産売却
- 【売却査定】インターネットで『不動産売却の無料一括査定 最大10社』のサイトを見たのですが、一番高い価格を出してくれる不動産業者にまかせておけば大丈夫でしょうか?
- 査定してもらう利用者は無料ですが、査定業者は運営会社に1件数万円の費用を支払って、売却希望者の情報を購入しています。
多数の業者から仕事中にもかかわらず、我先にと何社からも電話がかかってくるので対応に困るなど、強引でしつこい営業スタイルの会社があるのも事実です。
ここでの注意点は、最初から売却依頼を取ることだけが目的で、相場を無視した高額な査定価格をしたり、他社に物件を扱わせないように「囲い込み」をする悪質な業者に注意することです。
- 【売却のコツ】居住したまま売りに出していますが、注意点があれば教えてください
- 高額なお買い物をする内覧者様には、第一印象が肝心ですので、綺麗なスリッパを用意しておくなど、まずは玄関から片付けていくようにしましょう。
内覧者様が、これからの生活をイメージしながら内覧時間を過ごして頂くためにも、ちょっとした気遣いが、値引きを避けた高値売却につながっていきます。
- 【売却のコツ】売却するには、リフォーム工事が必要でしょうか?
- 印象のよくなるリフォームは有効ですが、リフォームにはお金と時間がかかります。
水廻りがキレイになっているだけで評価はガラリと変わりますので、水廻りのクリーニングくらいを検討してみてはいかがでしょうか。
お庭の手入れは、庭木の剪定や伸びた雑草を除去するだけでも、印象がよくなります。
地域のシルバー人材センターなどを利用する方法もあります。
- 【売却期間】不動産を売却して、相続税の納税資金にあてようと考えているのですか注意点は?
- 相続税の納税の期限は10か月ですが、日本人の風習で49日はお金の話はしないというものがあります。
不動産売買の習慣では、契約から引き渡しまで約1か月位かかり、 売却の手続きを進める前に通算約3か月は販売期間に使えなくなり、 残り7か月の間に売却しなければなりません。
不動産を売却する際には、隣地との境界を確定したり、越境や私道などがあれば覚書をとったりすると、あっという間に時間が過ぎ、販売期間が短くなり、安く売らなければいけないという状態になりかねませんので、余裕を持って、早めの行動をお勧めします。
- 【リースバック】住宅ローンの支払いが苦しいので、テレビのCMでよく見かけるリースバックしようと考えているのですが・・
- リースバックとは 売却した相手に毎月の家賃を支払い住み続ける制度で、主に不動産会社が買主になる取引になります。
自宅を売却することによりローンの支払いができ、引越しが必要なく周りに売却したことが知られない、税金や管理費等の維持費を支払う必要がなくなるということがメリットのようです。
デメリットもあり、買取となるため売却金額が通常より安く、支払う家賃が周辺の相場よりも高い場合もあります。
また契約内容によっては、定期借家契約で住み続けることが出来ない契約になっていたり、修理費は借主が負担する契約になっていることやオーナーが変わり家賃がさらに高くなったりすることもあります。
まだまだ使われることの少ない取引で、他に任意売却等の方法もありますの熟考が必要です。
- 【譲渡所得】親から相続した不動産を売却したいのですが、取得費不明の場合の『5%ルール』とは何ですか?
- 不動産を売却したときに、「購入価格(取得費)」より「売却価格」が高い場合、その差額に譲渡所得税がかかります。
相続不動産で親が買った時の契約書や領収書が見当たらず取得費が不明な場合は、売却価格の5%を購入価格とする「5%ルール」を適用しなければなりず、譲渡税が多額になってしまいます。
このような場合は、不動産鑑定士の『意見書』を利用する方法もあります。
意見書作成費用はかかりますが、意見書作成費用より節税額の方が多い場合は利用した方がお得ですので、早めのご相談をおすすめしております。
相続コンサルティング
- 【相続人廃除】私は息子に虐待されています。私の死後、遺産を譲りたくないので相続権の遺留分を奪うことは可能でしょうか
- 推定相続人の廃除、または廃除の取り消しをすることができます。
廃除とは遺留分をもつ推定相続人が被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えた場合や、法定相続人にその他の著しい非行があった場合に家庭裁判所に請求して相続権を奪う制度です。
生前行為によってすることもできますが、遺言によってすることもできます。
- (内縁関係)もし自分が亡くなった場合、内縁関係のパートナーに相続権はありますか?
- 本人が亡くなった時点で法的な婚姻関係がなければ、内縁のパートナーは相続できずに、本人の親または兄弟姉妹が法定相続人となります。
法定相続人がいる場合には「遺留分」がありますが、親がいない場合は遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、財産をパートナーにすべて渡すことができます。
もうひとつの手段は、生命保険金の受取人をパートナーに指定することによって、確実にパートナーの手に渡り、あなたの想いを形に残すことは可能です。
- (小規模宅地等の特例)居住用の特例を利用する際の要件、手続きと注意点があれば、教えてください
- 要件としては、居住用の場合は面積が330㎡までになり、被相続人が亡くなるまで居住していたことも要件になり、手続きでは、特例は自動的に適用されるわけではないので、相続税申告書に特例の適用を明記することが必要です。
注意点としては、相続人が申告期限までに自宅に居住していなかったり、相続後すぐに土地を売却してしまった場合、否認されることがあります。
この特例は、亡くなってからでは間に合わないケースも多いので、同居していない子どもに相続させる予定であれば、早めに居住実態を作ることや遺言書で取得者を明記しておくなどの準備が、家族の生活と財産を守る最善の策になります。
- (アパート建築)ハウスメーカーから土地と建物の相続税の評価の引き下げができると提案を受けて、駐車場にアパートを建てる予定です。本当に相続税の節税効果があるのでしょうか?
- アパートを建築することによって、相続税の評価額は下がりますが、それ以上に不動産の価値が下がります。
多くの人は、相続対策前の相続税と、相続対策後の相続税を比べて、相続対策後の相続税が下がっていたら節税と思っていますが、アパート建築で相続税が下がっているのは、資産の価値が減っているので、相続税が減っているだけです。
本当の節税とは、資産の価値はなるべくそのままで、相続税だけが減っている状態にすることです。
- (相次相続控除)父が亡くなって、1年も経たないうちに母が亡くなりました。父がなくなったときに相続税を納めましたが、母が父の財産を相続したときの財産にまた相続税がかかるのでしょうか?
- 10年以内に相次いで相続が発生する場合は、同じ財産に二重の相続税が課税されることになり、その負担を軽減するために、一定金額を相続税から控除できるのが『相次相続控除』です。
一次相続から二次相続まで1年未満なら一次相続で払った相続税分が100%控除され、その後は1年につき10%ずつ差し引いた額が相続税額から控除されます。
- (配偶者居住権)夫が亡くなり、子供が私を老人ホームに入居させると言い出しました。どうも私を追い出して、自宅を売ろうとしているようなのですが、私は住み続けたいです。何か方法はありませんか
- 子供が所有権を取得し、母親が配偶者居住権という権利を登記をすれば、母親は亡くなるまで無償で住み続けることができる権利です。
母親が亡くなったときは、配偶者居住権は消滅し、子供は売却することも可能となりますが、配偶者居住権を利用するには、父親が遺言書に残しておくか、遺産分割協議で合意する必要があります。
- (小規模宅地の特例)父親は数年前に亡くなり、実家に母親が一人で暮らしていますが、母親にもしものことがあったときは小規模宅地等の特例を適用できますか?
- 配偶者か同居親族が自宅を相続する場合、『小規模宅地等の特例』を適用することで土地の評価を80%下げ、土地にかかる税金を大幅に減らすことができる制度ですが、実家とは別の持ち家に住んでいる子供が相続する際には『小規模宅地等の特例』は適用されません。
しかし、子供が持ち家でなく、賃貸住宅に住んでいる場合はいわゆる『家なき子特例』に該当し、親と同居していなくても一定の条件をクリアすれば小規模宅地等の特例が使うことができますので、家族で事前に相談しておきましょう。
- (二次相続)父が亡くなったので、母にひとまず全財産を相続してもらおうと思うのですが、母が亡くなったときに相続税が多額になるって本当ですか?
- 母が亡くなったとき(二次相続)での税金が高くなる理由として、父が亡くなったとき(一次相続)には配偶者控除の特例(配偶者は1億6000万円まで相続税がかからない)を利用できるが、(二次相続)では配偶者がいないので、税額控除の特例が使えないこと。
また、(一次相続)時と比べて法定相続人が1人減り、基礎控除額が下がることと実効税率が変わることで相続税が高くなる可能性があります。
- 【障害者保護】夫は他界しており、子供が2人いますが1人は障害をもっております。
相続財産は遺言で平等に相続できるようにしていますが、障害者の子供はお金の管理ができないので心配です・・・ - 遺言で障害者の子供に何を相続させるかは指定出来ますが、どう管理するかはまでは指定出来ません。
そういう時は家族信託を使い、障害者の子供の兄弟を受託者として、健常者の兄弟が管理するという指定が出来ます。
遺言は必須の対策ですが、家族信託で遺言を補う事が出来きます。
- 【相続税試算】ハウスメーカーで、相続税の無料試算をしてもらったところ3,000万円と言われました、本当かどうかチェックしてもらえますか
- 弊社で計算した結果、相続税は70万円です。
ハウスメーカーの試算表には、小さい字で『小規模宅地特例は考慮しておりません』と書いてありましたが、今回は小規模宅地特例が使える状況にありますので、計算結果が大きく変わりました。
きちんとした現状分析を出すのには、無料試算で算出されたものを鵜呑みにするのは、要注意です。
- 【遺留分】父の遺言書に「長男は親不孝だったので、1円も相続させません」と書いてありました。本当に1円も相続できなのでしょうか?
- 遺言書があったとしても、「残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は必ず相続できる」という遺留分の権利があります。
遺留分は法定相続分の半分で、相続人が配偶者と子どもであれば、配偶者の法定相続分は2分の1、その半分の4分の1が遺留分。
子どもの法定相続分は2分の1、兄弟2人の場合、1人あたり4分の1です。遺留分は法定相続分の半分なので8分の1になります。
ただし遺留分侵害額の請求は、、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方に通知することが必要です。
- 【家族信託】私は現在、後妻と前妻の子と生活しています。
自分に万が一の事があったら、財産は後妻に相続させたいと思っていますが、後妻が亡くなった時には前妻の子に相続させたいと思っていますがどうすればよいでしょうか?
- まず、後妻と前妻の子で養子縁組をしなければなりませんが、養子縁組をしたとしても、後妻が遺言などで他の人を指定すると、前妻の子が相続出来なくなるかもしれません。
こういう時は家族信託を使い、委託者を父、受託者を前妻の子、受益者を当初は父、父が亡くなったら後妻、後妻が亡くなった後は前妻の子にします。
このような信託にする事で、後妻が亡くなった後も確実に、前妻の子に、財産を遺す事が出来ます。
- 【贈与額】 生前贈与で一番節税出来る贈与額って、110万円ですか?
- 110万円というのは、あくまでも非課税になる額です。
一番節税出来る額というのは、生前贈与をしていない場合の相続税と、生前贈与をした場合の贈与税と相続税の合計に一番乖離が出る額です。
- 【非課税枠】生前贈与の非課税枠が変わり、2倍になったとのことですが?
- 相続時精算課税制度にも110万円の非課税枠が新設されたので、暦年贈与の110万円とは別の制度になり、併用が出来るようになりました。
例えば、父からは相続時精算課税制度で110万円、母からは暦年贈与で110万円、という形で贈与を受ければ、どちらの贈与も非課税になり、110万円の非課税を2倍使うことができます。
- 【金銭貸借】息子がマンションを買うのに、住宅ローンの金利がもったいないので私がお金を貸してあげて、毎月私に返済するようにしたいのですが・・・
- 親子間で金銭の貸し借りをする場合は、贈与税がかからないようにするために、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成する。
借用書には、借入金額、返済期限、利息、返済方法などを明記し、印紙を貼り、実印で押印し、公正証書にする必要はないが、契約日を証明するために「確定日付」を取ると証拠能力が上がります。
現金で返済すると証拠が残らないため、返済実績を証明するために、毎月の返済を銀行振り込みで行い、通帳に記録を残しましょう。
- 【納税資金】今現在納税資金はありますが、将来的に心配なのですが・・・
- 今は、相続税を支払う現金があったとしても、将来的には現金が増える人もいれば、減る人もいます。
減る人であれば、今現在相続税を支払う現金があっても、将来足りなくなる事を想定して、今から対策をする必要があるかもしれません。
今だけを切り取る単年度の考え方ではなく、今現在から将来の相続税の額、現預金の額を把握する事が重要です。
現預金、有価証券、生命保険などの現金化しやすい財産である流動資産と相続税が、いつ足りなくなるかが分かるようにデータ化しておくことが重要です。
- 【収益不動産】現金をすべて不動産に変えておけは、良いのでしょうか?
- そうとは限りません。
例えば、不動産を買ったことで相続税を減らせたとしても、その不動産を売却した時に節税額以上に不動産価値が下がっていれば、結果的に損をしたことになります。
弊社では、相続税を減らす目的だけで、賃貸不動産は買うべきではないと考えています。
- 【相続税評価】現預金で相続させるよりも、不動産や生命保険で相続させた方が、どうして相続税は安く済むのですか?
- その理由は、不動産の時価と相続税評価額の差があるからです。
例えば1億円で購入した不動産は、相続税を計算する時に使う評価額にすると、高くても8,000万円位にしかなりません。
実際に売買する時の金額よりも、相続税の評価額は低く算定されるようになっています。